第一部 公理一
原文
Omnia quæ sunt vel in se vel in alio sunt.
自訳
すべての在るものはそれ自身においてあるか、あるいは他においてある。
語釈
in se それ自身において。これは第一部 定義三のsubstantia(実体)に直結する。「存在するために他を必要としない」
in alio 他において。これは第一部 定義五のmodus(様態)に直結する。「存在するために他を前提にする」
工藤・斎藤訳註に『実体とその変様との関係は、水と波との関係と同じようなものと考えられている』とある。
vel … vel … 排他的選言「AかBかのいずれか」。
velは「または」だが、二度繰り返すことで「~か、あるいは~」を示す。
哲学的には排中律的な二分。
スピノザは存在の基本的分類として「自存か他存か」を提示している。
解説
この公理に関して、私自身の興味としてはヘーゲル的「即自(An sich)」と「対自(Für sich)」の弁証法的構造との対比にある。
以下にまとめておく。
スピノザの in se / in alio とヘーゲルの An sich(即自) / Für sich(対自) を並べると、たしかにどちらも「自己」と「他者」あるいは「自存」と「依存」をめぐる区分を含んでいる。しかし両者の論理の動きはまったく別のメカニズムでできている。
スピノザの構図
- in se は「自らの概念が他を必要としないもの」。これは「実体(substantia)」=神=自然を指す。
- in alio は「他のものの中にあるもの」で、様態(modus)を示す。
- この二分は固定的で、実体と様態のあいだに移行や生成のプロセスはない。実体は永遠に自己原因的であり、様態は永遠に他因的である。論理的秩序(causa sui/必然性)であり、歴史的・時間的な発展ではない。
ヘーゲルの構図
- An sich(即自)は「それ自体としてあるが、まだ自己意識に至っていない状態」。
- Für sich(対自)は「自分が自分であることを知り、自分を対象化する状態」。
- ヘーゲルでは、存在はまず即自として与えられ、それが否定や対立を通じて自己を対象化し、対自へと移行し、最終的に「即且対自(An und Für sich)」に統合される。ここには生成と発展の弁証法がある。概念は自らの他者性を通して自己を実現する。
共通点と差異
共通点は、「自己完結」と「他者依存」をめぐる二項対立が出発点になっていること。
しかしスピノザはこの対立を論理的枠組みとして永遠に維持するのに対し、ヘーゲルは対立そのものを運動させて止揚する。
スピノザにおける様態は実体に還元されて終わりだが、ヘーゲルにおける即自は必ず対自へ、そして統合へ向かう。
要するに、スピノザの in se は「始めから完全に自己であるもの」であり、ヘーゲルの An sich は「自己だがまだそれを知らない未熟態」。この時間性の有無が二人の世界観の決定的な分岐点となっている。
ヘーゲル自身もスピノザの「実体」を「概念の運動が欠けている」と批判している。ヘーゲルにとってスピノザの in se は「An sich(即自) のまま固定された存在」ということになる。
言い換えると、ヘーゲルの「即且対自 An und Für sich」 は「スピノザ的 in se を歴史的弁証法に投げ込み、自己展開させたもの」と見ることもできる。両者を並べて考えると、存在を「最初から完成」と見るか「運動による自己実現」と見るか、哲学的立場の根本的な違いが浮き彫りになる。
ヘーゲルの An sich(即自) / Für sich(対自)等については過去記事参照。
第一部 公理二
原文
Id quod per aliud non potest concipi, per se concipi debet.
自訳
他のものによって考えられることができないものは、それ自身によって考えられねばならない。
第一部 公理三
原文
Ex data causa determinata necessario sequitur effectus et contra si nulla detur determinata causa, impossibile est ut effectus sequatur.
自訳
限定されて与えられた原因から結果が必然的に出てき、反対にもし限定された原因が何も与えられないならば結果が出てくることは不可能である。
語釈
& contra 反対に。古典ラテン語でよく出てくる慣用表現。
si nulla detur 接続法現在能動態。もし何も与えられないとすれば。
「仮定的・可能的な条件を示す条件文における接続法。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p291 観念的条件文)
ut + 接続法 「〜すること」「〜するように」の従属節を作る。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p276 utやnēの導く名詞的目的文)
第一部 公理四
原文
Effectus cognitio a cognitione causæ dependet et eandem involvit.
自訳
結果の認識は原因の認識に依存し、そして同じもの〔原因の認識〕を含む。
語釈
dependet 第3変化動詞dependeo(たれさがる、依存する、由来する)の三人称単数。
involvit 「原因の概念が結果の概念の中に構造的に含まれている」ことを指す。結果の「真の認識」は必然的に原因の概念と同時に与えられるということ。
解説
スピノザにおける「真の認識」とは、単なる経験的な事実把握ではなく、原因を通して結果を必然的に理解する知識(第二種の認識=ratio)を指す。
その認識論が極めて存在論的であることを示している箇所でもある。
ここで言う「存在論的」というのは、Aという観念とBという観念からCという観念が結果的に出てくるような観念のネットワークを指す。(もちろん実際にはより複雑なネットワークになっているのだが)
そしてスピノザの心身並行論とは、そのような観念の秩序(ネットワーク)が存在の秩序と一元的な対応関係にあるということ。
第一部 公理五
原文
Quæ nihil commune cum se invicem habent, etiam per se invicem intelligi non possunt sive conceptus unius alterius conceptum non involvit.
自訳
互いに何の共通するところも持たないものどうしは、互いが互いによって理解されることができず、言い換えれば一方の概念は他方の概念を含まない。
語釈
Quæ 関係代名詞quī の中性複数主格。ここでは先行詞が明示されておらず、ラテン語では、人や物を特定しない一般的な「もの」「事柄」や、抽象的・集合的な内容を受けるとき中性複数 quae がよく使われる。
三人称複数の動詞 habent によっても quae =複数主格は確定する。
cum se invicem cum(〜とともに)+ se(互いに相手を)+ invicem(相互に) の三重の相互表現。
「互いに共通性を共有していない」という否定を最大限に強調するためにこのような表現になっている。
解説
この公理は属性間の独立性を主張する鍵となる。公理四で解説した「観念の秩序(思惟)」と「存在の秩序(延長)」も一元的な対応関係にはあるが、お互いの属性を跨いで影響を与え合うことはない。
だから「思惟の概念」から「延長の概念」を推論することはできない。
したがって精神と身体は因果的には「並行」するだけで、一方から他方を説明することはできない。この前提が心身並行論を支える。
第一部 公理六
原文
Idea vera debet cum suo ideato convenire.
自訳
真の観念はその観念対象と一致しなければならない。
解説
idea が「心の中の表象」であるのに対し、
ideatum は「その表象が向かう対象」「観念されるもの」を指す。
idea と ideatumは意識の内と対象の側を区別するペア。
- 例:idea equi(馬の観念)とその ideatum(馬そのもの)。
- ただし「馬」という外的物体に限らず、「三角形の本質」や「神の属性」など抽象的対象も含む。
スピノザにとってこの二分法は単なる主観/客観の対立ではない。
彼は心身並行論を採るため、観念(idea)とその対象(ideatum)は
実体(神=自然)の二つの属性(思惟/延長)における同一の事態を示す。
したがって「観念の対象」といっても、外にある別物というより、
同一存在の異なる表現様態。
この公理は、 「真の観念はその対象(ideatum)と一致する」という外的照合ではなく、 同一の必然性の二側面の一致を指す。
第一部 公理七
原文
Quicquid ut non existens potest concipi, ejus essentia non involvit existentiam.
自訳
存在しないものとして考えられることができるものは何であれ、その本質は現実存在を含まない。
語釈
quicquid 何であれ。すべて。第一部 定義六の語釈参照。
ut + 分詞(または形容詞) ~として。~のように。という様態・状態を示す。
解説
スピノザは「あるものの本質が存在を必然的に含むか否か」で、神と有限存在を区別する。
「存在しないものとして想定可能なもの」は、その概念に存在の必然性が含まれていない、すなわち偶然的存在である。
逆に言えば、存在を含む本質は「存在しない」と想定することができない。それがスピノザにおける神=実体の定義(第一部 定理一一)につながる。
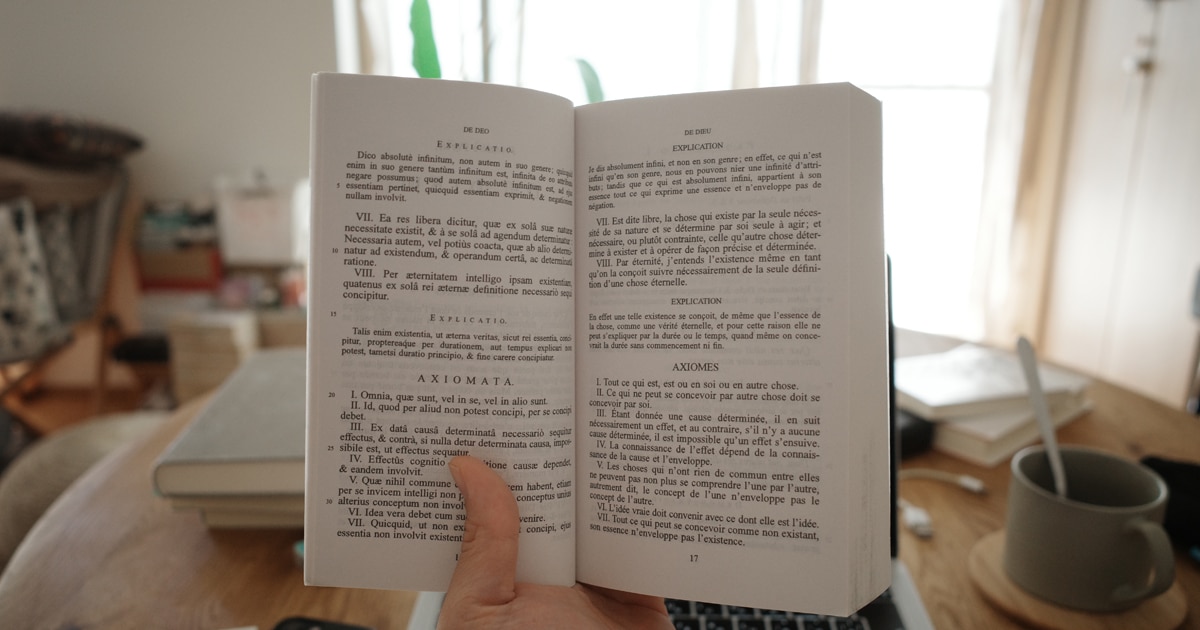




コメント