第一部 定理一
原文
Substantia prior est natura suis affectionibus.
自訳
実体は本性において、その変状より先立つ。
語釈
prior 比較級で「より先の、より前の」。単なる時間的な「先に生じる」ではなく、論理的・形而上学的な優先性を示す。
natura 女性単数奪格。「限定の奪格」(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p338 限定の奪格)
suis affectionibus 女性複数奪格。比較級の構文で「〜より」を意味する「比較の奪格」をとる。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p239,p334 比較の奪格)
実体には無限に多様な様態が含まれるため、一つのaffectioではなく無数のaffectionesを前提するのが自然なため複数形になっている。
また、所有形容詞suisは「実体」を指すが、「実体はひとつ」なはずなのになぜ複数形になっているのかと疑問が浮かんだ。
調べてみると、所有者が単数(実体=substantia)であっても、所有物(affectiones)が複数なら、 所有形容詞も複数に一致させるラテン語の文法上の原則のためであった。
証明 原文
DEMONSTRATIO : Patet ex definitione 3 et 5.
証明 自訳
証明:それは定義三と五から明らかである。
第一部 定理二
原文
Duæ substantiæ diversa attributa habentes nihil inter se commune habent.
自訳
異なる属性を持つ二つの実体は、それらの間で共通点が何もない。
語釈
habentes 現在分詞。複数主格。Duæ substantiæ を修飾。
証明 原文
DEMONSTRATIO : Patet etiam ex definitione 3. Unaquæque enim in se debet esse et per se debet concipi sive conceptus unius conceptum alterius non involvit.
証明 自訳
証明:それも定義三から明らかである。なぜなら、〔それら実体の〕ひとつひとつそれぞれがそれ自身においてあり、それ自身によって考えられねばならず、言いかえれば、一方の概念は他方の概念を含まないからである。
語釈
Unaquæque una + quaequeの複合語。unus, -a, -um(「一つの」「各一の」)の女性・単数・主格 una。
quaeque は quisque/quaeque/quodque(「それぞれ」「各々」)の女性・単数・主格 quaeque 。
単なる quaeque よりも「一つ一つのそれぞれ」という個別性を際立たせるニュアンスがある。
性が女性になるのは、女性名詞であるsubstantiæ(実体)を指すから。
alterius (二つのうち)他方の。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p137 代名詞的形容詞)
第一部 定理三
原文
Quæ res nihil commune inter se habent, earum una alterius causa esse non potest.
自訳
互いのあいだで何も共通のものを持たない事物は、それらの一方が他方の原因であることはできない。
語釈
Quæ 関係代名詞 qui の女性複数主格。第一部 公理五の関係代名詞 quae は先行詞が省略されていたがこちらの場合直後の res(女・複・主) が先行詞になっている。
証明 原文
DEMONSTRATIO: Si nihil commune cum se invicem habent, ergo (per axioma 5) nec per se invicem possunt intelligi adeoque (per axioma 4) una alterius causa esse non potest. Q.E.D.
証明 自訳
証明:もし互いに何も共通なものを持たないなら、それゆえ(公理五により)互いが互いによって理解されることもできない。こうして(公理四により)一方は他方の原因であることはできない。これが証明されるべきことであった。
語釈
cum se invicem cum(〜とともに)+ se(互いに相手を)+ invicem(相互に) の三重の相互表現。
「互いに共通性を共有していない」という否定を最大限に強調するためにこのような表現になっている。第一部 公理五と同様の表現。
per se invicem 第一部 公理五の語釈参照。
Q.E.D. 『これはQuod erat demonstrandum すなわち「これが証明されるべきことであった」の意である。ユークリッド の用法に倣ったものとみられる』と畠中訳註にある。
Quod 関係代名詞。中性単数主格。
erat 動詞 sum の三人称単数・未完了過去。
demonstrandum 動形容詞(受動の義務を意味する)。中性単数主格。
解説
第一部 公理五を元にする定理。後の定理とともに単一実体(神)論へ橋渡しする役割を果たす。
第一部 定理四
原文
Duæ aut plures res distinctæ vel inter se distinguuntur ex diversitate attributorum substantiarum vel ex diversitate earundem affectionum.
自訳
区別される二つあるいは多くの事物は、諸実体の属性の相違から互いのあいだで区別されるか、同じもの〔諸実体〕の変状の相違から区別されるか、そのいずれかである。
語釈
distinctæ 動詞 distinguo の完了受動分詞。
vel … vel … 排他的選言「AかBかのいずれか」。
diversitate 第三変化名詞 diversitas 。女性単数奪格。相違。
earundem 指示代名詞 idem の女性複数属格。同じ、同じもの。
証明 原文
DEMONSTRATIO: Omnia quæ sunt vel in se vel in alio sunt (per axioma 1) hoc est (per definitiones 3 et 5) extra intellectum nihil datur præter substantias earumque affectiones. Nihil ergo extra intellectum datur per quod plures res distingui inter se possunt præter substantias sive quod idem est (per definitionem 4) earum attributa earumque affectiones. Q.E.D.
証明 自訳
証明:すべてあるものはそれ自身においてあるか、他においてあるかのいずれかである(公理一により)。すなわち(定義三と五により)知性を除くと諸実体とそれらの変状のほかには何も与えられない。それゆえ実体のほかには知性を除いては何も与えられない。複数の事物が互いのあいだで区別されうるような〔手段としては〕何ものも〔与えられない〕。〔実体を〕言い換えれば同じことであるが(定義四により)それらの属性とそれらの変状〔のほかには何ものも与えられない〕。これが証明されるべきことであった。
上野訳(参考訳)
証明:すべてあるものはそれ自身においてあるか、他においてある(公理一により)。すなわち知性の外にはもろもろの実体とその変状のほかには何も与えられない(定義三と五により)。ゆえに複数の事物が区別できるために知性の外に与えられるものとしては、もろもろの実体、言いかえれば同じことだが(定義四により)それら実体の属性、およびそれら実体の変状のほかには何もない。証明終わり。
語釈
per quod plures res distingui inter se possunt この部分がNihil … datur (何も与えられない)にかかってくる。
sive quod idem est (per definitionem 4) earum attributa earumque affectiones.
「諸実体」と「それらの属性とそれらの変状」とは定義四によれば同じものを指す、という言い換えをしている箇所。
præter substantias earumque affectiones earumque(複数)。『遺稿集』ラテン語版とヴァチカン写本では ejusque (単数)になっている。
『定理八の備考二で述べられるように「実体」は定義の上では数を含まず、 複数存在しえないという証明に至るまでは個数が不定にとどまる。』と上野訳註にある。
解説
「実体と属性と様態以外には知性しかない」と読めてしまう余地があるがスピノザの意図はそうではない。
extra intellectum (知性を除くと)という表現は、「観念における領分」と「存在論的な領分」を区別する意図を持つ。
ここで「知性を除く」とは、「これは我々の思考操作によらない存在論的な領分の話ですよ」という前置きのようなものである。
スピノザは、存在を「知性の外」と「知性の内」とに分け、外に関して「実体+属性+様態」以外はない、と限定している。
つまり「内」には「知性そのもの(=思惟の一様態としての知性作用)」があるが、それを“存在の種類”として実体・属性と並列しているわけではない。
スピノザにとって知性はCogitatio(思惟)という属性の一様態に属する。
つまり人間の知性は「思惟属性の変状(affectio)」として、すでに「実体+属性+様態」の三分法の内部に位置づけられている。
したがって知性を「実体と別の第四のもの」とみなすことはできない。
第一部 定理五
原文
In rerum natura non possunt dari duæ aut plures substantiæ ejusdem naturæ sive attributi.
自訳
諸事物の本性において、本性ないし属性が同じである二つまたは多数の実体が与えられることはできない。
語釈
ejusdem 指示代名詞 idem の単数属格。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p325 性質の属格)
naturæ sive attributi naturæ も attributi も単数属格。「複数の実体が共有してしまう一つの本性/属性」という意味。
証明 原文
DEMONSTRATIO: Si darentur plures distinctæ, deberent inter se distingui vel ex diversitate attributorum vel ex diversitate affectionum (per propositionem præcedentem). Si tantum ex diversitate attributorum, concedetur ergo non dari nisi unam ejusdem attributi. At si ex diversitate affectionum, cum substantia sit prior natura suis affectionibus (per propositionem 1) depositis ergo affectionibus et in se considerata hoc est (per definitionem 3 et axioma 6) vere considerata, non poterit concipi ab alia distingui hoc est (per propositionem præcedentem) non poterunt dari plures sed tantum una. Q.E.D.
証明 自訳
もし区別される複数のもの(実体)が与えられていたならば、それらは互いに属性の相違からか、変状の相違からかのいずれかによって区別されねばならない(前定理により)。もし〔区別が〕ただ属性の相違のみしかないならば、同じ属性の〔実体は〕一つを除いては与えられないと認められるだろう。しかし、もし〔区別が〕変状の違いから〔のみしかない〕ならば、実体は本性においてその変状に先立つ(定理一により)のだから、変状を捨象し〔実体が〕それ自身において考察される限り、すなわち(定義三と公理六により)〔実体が〕真に考察される限り、他のもの〔他の実体〕から区別されると考えることはできないだろう。すなわち(前定理により)複数の〔実体〕があたえられることはできず、ただ一つのみ〔与えられうるだろう〕。これが証明されるべきことであった。
語釈
Si darentur … deberent 接続法の復文での用法。主文(deberent…)が第二時称(未完了過去)で従属文(Si darentur…)も未完了過去なので、「同時」の内容を表している。また、「複数の実体を想定する」という事実に反する仮定を行なっているため主文、従属文ともに接続法、未完了過去が使われている。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p269 接続法の復文での用法、p291 非現実的条件文)
per propositionem præcedentem 前定理により。præcedentemの原型はpraecedo (先行する)。現在分詞(praecedens, praecedentis)の女性単数対格。
tantum ただ〜のみ。
Si tantum ex diversitate attributorum, 主文、従属文ともに直接法。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p290 論理的条件文)
cum substantia sit prior natura suis affectionibus 〜なので。cum は接続法を用いた理由文を導く。natura は限定の奪格(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p338 限定の奪格)。
depositis ergo … vere considerata 絶対的奪格構文。「〜が…された状態で」
理由や時、条件や譲歩などの接続詞がないため、どの意味で理解するかは文脈を頼りにして判断する。
解説
In rerum natura
『「物の自然のうちには (in rerum natura)」は、前の命題四の論証にある「知性のそと (extra intellectum)」 と同じ事柄を指し、外の自然である対象界を意味していると思われる。「外」というのは神の無限な知性とわれわれの有限な知性(ともにそれぞれの「内」の自然)にとっての「外」である。』と佐藤訳註にある。定理四の解説も参照。
この定理では in se considerata と vere considerata を等値化しており、実体の真なる(vere)認識がその存在様式(in se)に一致する、というスピノザの認識論的前提そのものとなっている。in se は定義三を、vere は公理六を踏まえた哲学的表現である。
- in se considerata
定義三では実体が「他に依存しない存在」であり「他に依存しない概念」であるとされる。存在と概念がともに自立的であるということ、つまりin se considerata (考察する)とは、実体を「何ものにも依存せず、純粋にそれ自体として思惟する」ということ。
この「考察」は、単なる知的操作ではなく、実体の存在構造を模倣する思考のあり方である。 - vere considerata
公理六では、「真の観念はその観念対象と一致しなければならない」とされる。
vere considerata とは、実体を「真なる観念によって考察すること」、つまり、思考内容が観念対象(実体そのもの)と一致している状態を意味する。
in se considerata hoc est vere considerata
「in se considerata = vere considerata」スピノザはこの二つを等号でつないだ。
これは単なる言い換えではなく、「存在と思考の一致」を、文法的同格(hoc est)という形で示した。
「実体をin seとして考えること」=「それを真に(真理として)考えること」
それが第二部 定理七「観念の秩序と連関は、事物の秩序と連関と同一である」の先取りになっている。
二つ目のhoc est
in se considerata と vere considerata の概念的区別不能性を存在論的唯一性に変換するための論理的転換のスイッチとして使っている。hoc est によって他の言い回しに言い換える=より厳密な概念に“移す”という役割があり、スピノザ特有の「必然性の生成」の役割を担っている。
第一部 定理六
原文
Una substantia non potest produci ab alia substantia.
自訳
一つの実体は他の実体から生み出されることはできない。
証明 原文
DEMONSTRATIO: In rerum natura non possunt dari duæ substantiæ ejusdem attributi (per propositionem præcedentem) hoc est (per propositionem 2) quæ aliquid inter se commune habent. Adeoque (per propositionem 3) una alterius causa esse nequit sive ab alia non potest produci. Q.E.D
証明 自訳
諸事物の本性において同じ属性の二つの実体――すなわち(定理二により)互いの間で何かある共通なものを持つ〔二つの実体〕――が与えられることはできない(前定理により)。こうして(定理三により)一方が他方の原因であることはできない。言い換えれば、他のものによって生み出されることはできない。これが証明されるべきことであった。
解説
☆ alterius と alia の意味の区別について
一般的な意味の違いとして、
alterius
→ 「(2つのうち)他方の(other of two)」
alia
→ 「他の(other)」
同じ「他」でも、
alter = 二者関係の中での「他方」
alius = より一般的な「他のもの」
という差がある。
定理六の最後の文では、なぜ同じ「他」なのに語を変えているのか。
前半(alterius)
una alterius causa esse nequit
二つの実体があると仮定した場合の
相互因果の否定を示しており、
「AがBの原因」「BがAの原因」
どちらも不可。
後半(alia)
ab alia non potest produci
実体一般について
外部原因からの生成を否定しており、
「何か他のもの」から作られること自体が不可。
alter:関係的・対称的
alius:外在的・一般的
この切り替えで、
1.相互因果が無理
2.外因による生成も無理
という二段構えを、一文で重ねている。
ここから実体の絶対的独立性が確定する。
→ causa sui につながる。
・他のものが原因ではない
・他のものから産出されない
そうなると実体の存在は、自分自身の本性によって説明されるしかない。
これが causa sui
「自己が自己の原因である」というより
「存在の説明が自己完結している」
という意味につながる。
第一部 定理六 系
原文
Hinc sequitur substantiam ab alio produci non posse. Nam in rerum natura nihil datur præter substantias earumque affectiones ut patet ex axiomate 1 et definitionibus 3 et 5. Atqui a substantia produci non potest (per præcedentem propositionem). Ergo substantia absolute ab alio produci non potest. Q.E.D.
自訳
ここから実体は他のものから生み出されることはできないということが出てくる。
なぜなら、公理一と定義三と五から明らかなように、事物の本性において諸実体とそれらの変状の他に何も与えられない。ところで〔実体は〕実体から生み出されることはできない(前定理により)。ゆえに、実体は絶対的に他のものから生み出されることはできない。これが証明されるべきことであった。
語釈
substantiam 対格不定法。
ut patet ここでは、比較・例示・事実の ut として使われており直接法がとられている。
仮に ut pateatと接続法にすると、「明らかになるように(目的)」=「明らかにするために」という意味になり、ここでスピノザが行なっている「〜から明らかな事実として」述べている「事実叙述」の意図からはずれてしまう。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p286 比較文)
Atqui (三段論法において小前提を導いて)ところで。
例: 大前提: omnes homines mortales sunt. 人間はすべて可死的である; 小前提: atqui Gaius homo est [Gaius autem homo est]. ところで Gaius は人間である; 結論: ergo Gaius mortalis est. 故に Gaius は可死的である。
per præcedentem propositionem 定理五 証明や定理六 証明ではpræcedentem と propositionem の順序が逆になっている。文法的にはどちらも正しく、意味の違いはほとんどない。強調や文体的リズムの問題。
別の証明 原文
ALITER: Demonstratur hoc etiam facilius ex absurdo contradictorio. Nam si substantia ab alio posset produci, ejus cognitio a cognitione suæ causæ deberet pendere (per axioma 4) adeoque (per definitionem 3) non esset substantia.
別の証明 自訳
別の証明:これは背理・矛盾〔背理法〕からより容易に証明される。というのも、もし実体が他のものから生み出されることができるとしたら、その認識はその〔認識の〕原因の認識に依存しなければならないであろう(公理四により)。したがって(定義三により)〔それは〕実体ではないことになる。
語釈
ex absurdo contradictorio この部分の訳については、畠中訳の「反対の場合が不条理であるということから」が一番しっくりきた。
Nam si … non esset substantia. 接続法の復文での用法。下記解説参照。定理五の語釈も参照。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p291 非現実的条件文)
解説
ここにはスピノザの幾何学的秩序の三段構造がわかりやすく表れている。
以下のような三段構造が『エチカ』の証明を支えている。
仮定(接続法)→ 論理的反証 → 必然的結論(直説法)
- 仮定(接続法)
Nam si substantia ab alio posset produci, ejus cognitio a cognitione suæ causæ deberet pendere (per axioma 4)
『というのも、もし実体が他のものから生み出されることができるとしたら、その認識はその〔認識の〕原因の認識に依存しなければならないであろう(公理四により)。』 - 論理的反証
adeoque (per definitionem 3) non esset substantia.
『したがって(定義三により)〔それは〕実体ではないことになる。』 - 必然的結論(直説法)
Hinc sequitur substantiam ab alio produci non posse.
『ここから実体は他のものから生み出されることはできないということが出てくる。』
スピノザは必然的結論のところで sequitur を「直説法」で書いている。
これには非常に重要な意味がある。
もし接続法で Hinc sequeretur… と書けば、「ここから~が帰結するだろう(はずだ)」=仮に正しければそうなるだろうという未確定の推論になる。
つまり“論理的可能性”レベルの帰結すぎない。
それに対して直接法の Hinc sequitur… は、「ここから(実際に)~が帰結する」=必然的・実際的帰結。つまり論理的・形而上学的な真理の確定を意味する。
この文の sequitur が直説法であるという一点に、スピノザが「幾何学的必然性」と「形而上学的真理」を同一視している姿勢がうかがえる。
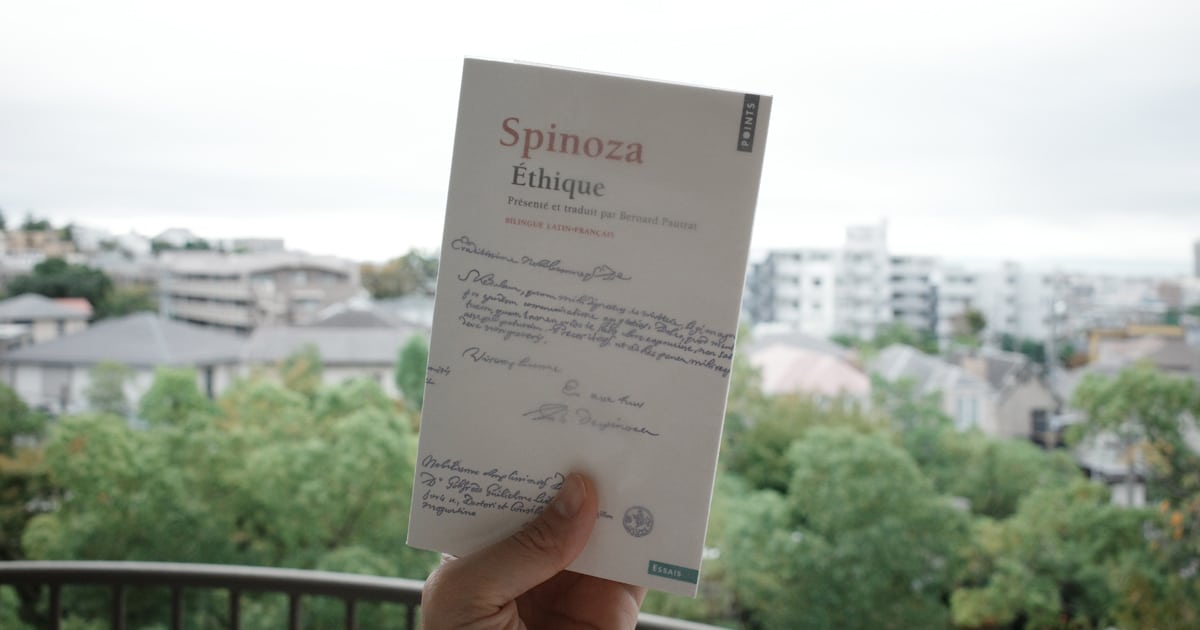



コメント