第一部 定義一
原文
Per causam sui intelligo id cujus essentia involvit existentiam sive id cujus natura non potest concipi nisi existens.
自訳
「自己原因」によって私は、その本質が存在を含むもの、言いかえれば、その本性が存在することのほかには考えられないものと理解する。
語釈
sui これは三人称の再帰所有形容詞 suus の属格ではなく、三人称の再帰代名詞の用法。
両者の違いは混同しやすいので以下に簡単にまとめておく。
suus,-a,-um(再帰所有形容詞)
「その主語自身の X」
所有の対象となる名詞に 一致(性・数・格) させて使う形容詞。
所有の対象(名詞)がある。
ex. Puella suum librum legit.
少女は 自分(=その少女) の本を読む。
(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p46 3人称の所有形容詞)
sui(再帰代名詞)
→「自分自身/自分自身のこと」
名詞の代わりに単体で使われる代名詞(性なし、単複同形、格変化のみ)
性区別なし。
単複で同形。
格だけが変化する。(sui/sibi/se/se)
所有される名詞がない時、名詞を置き換える代名詞として機能。
より抽象的・自律的な再帰性を表すことが多い。
ex. Per causam sui
自分自身の原因によって
(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p122 再帰代名詞の3人称)
intelligo 私は理解する。一人称単数。intellegoの異形。やや古風・地方的・詩的な表記の揺れとして現れる。対格支配で「理解する」の意。
既出訳の内、上野訳と佐藤訳では「私は」と一人称の主語の部分を訳に採用している。ここで言われる「私」とは誰なのだろうかという問題がある。もちろん普通に読んだら著者であるスピノザになるが、エチカ自体が幾何学的様式で記述され、数学の定理のように普遍的な内容の証明として書かれていると考えると、ここで言われる「私」が誰を指すのかわからなくなる。
sive 直訳では「すなわち、あるいは」。別の表現で言い換えるニュアンス。hoc estと区別すること。(第一部 定義三参照)
concipi 考えられること。concipio の現在、受動態、不定法。「精神の能動性」を表すconcipere⇔それに対して「精神の受動性」を表すpercipere(第二部 定義三)。しかしエチカの中ではこの区別はほとんど守られず、ともに「認識する」というほどの意味で使われている、と畠中訳註にある。
existens existoの現在分詞。単数主格。直訳では「現れる、生ずる」。ここでは形容詞の名詞的用法として使われる。
第一部 定義二
原文
Ea res dicitur in suo genere finita quæ alia ejusdem naturæ terminari potest. Exempli gratia corpus dicitur finitum quia aliud semper majus concipimus. Sic cogitatio alia cogitatione terminatur. At corpus non terminatur cogitatione nec cogitatio corpore.
自訳
同じ本性の他の〔事物〕によって限定されうるその事物は「その種類において有限」と言われる。
たとえば物体は、有限であると言われる。なぜなら、われわれはより大きな他の〔物体〕を常に考えるからである。
同様に思惟は、他の思惟によって限定される。しかし、物体が思惟によって限定されたり、思惟が物体によって限定されたりすることはない。
語釈
finita finioの完了受動分詞。「無限なるものに対して限定された存在」というニュアンス。内的・本質的な有限性。
terminari terminoの不定法受動態。「他との関係によって区切られる、境界線を引かれる」というニュアンス。外的・相対的な有限性。
exempli gratia たとえば。
alius,-a,-ud 他の(other)。代名詞的形容詞。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p136)
解説
スピノザにとってひとくちに「有限」といっても、上記のfinioとterminoは二重の意味を持っている。
同じような意味の語句でもそのニュアンスの違いによって訳し分けられている。このような違いはやはり原典にあたらないとわからない部分である。
日本語にすると同じような訳語でも原典において、ちがう単語が使われているということは、そこになんらかスピノザの意図があると考えなくてはならない。
第一部 定義三
原文
Per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur hoc est id cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei a quo formari debeat.
自訳
「実体」によって私は理解する。それ自身においてあり、かつそれ自身によって考えられるものと。すなわち、その概念が他の事物の概念を必要としないものであり、それ〔他の事物の概念〕によって形成されるべきではないものであると。
語釈
hoc est すなわち。
第一部 定義一にでてくるsiveとはニュアンスの違いがあるので区別すること。第一部 定理七の解説参照。
解説
デカルトの定義を踏襲した「実体」定義になっているものの、このあとに見られるようにスピノザにおいては存在の一義性が徹底されている。
第一部 定義四
原文
Per attributum intelligo id quod intellectus de substantia percipit tanquam ejusdem essentiam constituens.
自訳
「属性」によって私は、知性が実体について、あたかも同じもの〔実体〕の本質を構成しているもののように認識するところのものと、理解する。
語釈
percipit 認識する、認知する。
第一部 定義一でconcipioとの対比を述べたが、エチカでは広い意味で「それと見てとる」というくらいの意味で使われるとのこと。
tanquam あたかも〜のように。副詞。
解説
この定義に関して少し長いが畠中訳註を引用しておく。
『問題の多いこの定義については次の三つのことを記しておく。
A この定義の解釈にはエルトマンによって代表される観念論的解釈と、クノー・フィッシ ャーによって代表される実在論的解釈と二とおりあることは周知のごとくである。すなわち前者は属性を実体に関する知性の認識形式にすぎぬものとするのに対し、後者は属性を実体そのものの実在性を表現するものとしている。前者はスピノザをカントの立場に近づけるもので、 解釈自体としては興味あるものであるが、『エチカ』における他の諸個所はこの解釈に有利でなく、現今ではほとんどすべての研究者が後者すなわち実在論的解釈を採っている。
B しかしこの知性は単に我々の有限の知性だけではなく無限の知性も含めていること(これは第二部定理七の備考でこの定義が特に無限の知性に関連して言われていることからも明らかである)、したがって有限の知性は実体について有限数の属性を、無限の知性は無限数の属性を認識するという解釈だけは成り立つであろう。
C この定義の前後の諸定義にはみなconcipere (考える、概念する)というタームが用いられており、ここも当然そうあるものと期待されるのに、ここだけ特に percipere(知覚する)と なっている。もっとも、註(一)に言ったように、この両語はあとで混同されて用いられているのだから実質的にはどちらを用いてもいいわけであろうが、ただ注意すべきことは、N・S・ (オランダ語訳遺稿集)の台本となった原稿にはこの個所も concipere となっていることである 〔Bに言った無限の知性に関して言われている個所―———第二部定理七備考――もO・P・(ラテ ン語遺稿集すなわち原版エチカ)には percipere となっているが、N・S・の原稿には conci- pereとなっていた〕。つまりスピノザはもともと concipere と書いたものをそのあとで特に percipere と直したのである。なぜ彼が属性に関する知性の認識の場合だけ再三 concipereを percipere と改めたかの理由は今となっては我々にはっきりは分からないが、人によってはこれを、スピノザ自らあらかじめ、Aで言ったような観念論的解釈の起こるのを防ぐためにそうしたのだと見ている。例えばR. Wahle は「第一に、de substantia percipere (concipere とは 書かれていない!)という表現はこういう仮説〔観念論的解釈〕を成育させる余地を全然なからしめている云々」 (Kurze Erklärung der Ethik von Spinoza, p. 51)と言っている。』
第一部 定義五
原文
Per modum intelligo substantiæ affectiones sive id quod in alio est, per quod etiam concipitur.
自訳
「様態」によって私は、実体の変状、言いかえれば、他のものにおいてあり、かつそれ〔他のもの〕によって考えられるようなもののことと、理解する。
語釈
affectiones 変状。第3変化名詞affectioの女性複数対格。前のintelligoは対格支配で「理解する」。
畠中訳註に「すべてあるものが刺激ないし触発によって呈する一定の状態を言う」とある。
上野訳註に「精神的あるいは身体的変化の様式を意味するのに用いられていた語」とある。
解説
この定義に関して、工藤・斎藤訳註を引いておく。
『もともと様態とは、ものの存在の様式を表わすことばとして使われている。だがスピノザの形而上学の場合、それは一般に、神によって産出された有限者を意味している。実体がそれ自身において存存し、他のものを必要としないのに、様態は他のもの、つまり神のうちに存在する。またこの「・・・・・・ のうち」はたんに「・・・・・・の中にある」という意味ばかりでなく、スピノザの場合には、他に原因を必要とするという意味をもっている。また、この様態のことを彼は変様ともいっているが、変様とは、 ものが一定の形、状態において現われることを意味する。したがって実体の変様とは、実体を一定の仕方で表現するもの(第一部定理二五の系により)のこととなる。』
第一部 定義六
原文
Per Deum intelligo ens absolute infinitum hoc est substantiam constantem infinitis attributis quorum unumquodque æternam et infinitam essentiam exprimit.
自訳
「神」によって私は、絶対的に無限な存在者、すなわち、その一つひとつが永遠かつ無限な本質を表現する無限〔に多く〕の属性において成り立つ実体、と理解する。
語釈
ens 第三変化名詞、中性単数対格。存在者。上野訳註に「動詞 esse (ある)の分詞からできた語で、無ではなくとにかく何かである対象、という意味である」との記述あり。現に存在する、現実に存在するという意味の「存在」(existentia)と区別すること。(第一部 定義一)
absolutè 絶対的に。形容詞infinitumを修飾する副詞。
absolutum infinitum としなかったのは、定義六の説明にある相対的無限と絶対的無限を峻別するため。つまり「無限である、その仕方が絶対的に」という “様態の限定”をすることでabsolutèは「無限 (infinitum)」のあり方を規定している、とのこと。
constantem 現在分詞、単数対格。成り立つ。
attributis 複数属格。属性。起源の奪格として「属性から」や、手段の奪格として「属性によって」とも取れるが、ここでは上野訳に倣い「属性において」と場所の奪格として訳した。
説明 原文
EXPLICATIO: Dico absolute infinitum, non autem in suo genere; quicquid enim in suo genere tantum infinitum est, infinita de eo attributa negare possumus; quod autem absolute infinitum est, ad ejus essentiam pertinet quicquid essentiam exprimit et negationem nullam involvit.
説明 原文
説明:私は「絶対的に無限な」と言い、「その種類において〔無限な〕」とは言わない。なぜなら、何であれただその種類においてのみ無限なもの〔の場合〕は、それについてわれわれは無限〔に多く〕の属性を否定することができるが、絶対的に無限なもの〔の場合〕は、本質を表現し、いかなる否定も含まないあらゆるものであり、その本質に属するからである。
語釈
tantum ただ〜のみ。
quicquid 何であれ。すべて。
上野訳と佐藤訳は「何であれ」と訳している。「何であれ」と訳すと「任意性」のニュアンスが強く、「すべて」と訳すと「必然性」のニュアンスが強くなる。どちらの訳語を取るかによって訳のニュアンスの違い以上に、哲学的問題を含んでいる可能性があるようだ。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p219 不定関係代名詞)
以下のグッチさんという方のnote記事に詳しく書かれている。
in suo genere tantum infinitum「ただその種類においてのみ無限なもの」。相対的無限。
自然数の無限性、空間の無限延長はそれらの属性のなかにおいてだけ無限であり、「一つの属性や領域に限定された無限」なので、他の属性を欠いている『不完全な無限』である。
absolute infinitum「絶対的に無限なもの」
いかなる種類、属性にも限定されない、無条件の無限。
それは本質において無限に多くの属性を持ち、欠如や否定を含まない。
スピノザはこれを「神、すなわち実体」と同定する。
解説
ヘーゲルにおける「悪無限」「真無限」と、スピノザの「相対的無限」「絶対的無限」は違う概念なので区別すること。以下にまとめておく。
スピノザにおける「その種類における無限(相対的無限)」:
- ある属性に限定された無限。
- 例:数の無限、延長の無限、思惟の無限。
- それぞれが「他の属性」を欠いているから、限定されている。
スピノザにおける「絶対的無限」:
- いかなる限定も受けない無限。
- 本質において無限の属性をすべてもつもの。
- 否定を含まない。⇒ 神(Deus sive Natura)そのもの。
ヘーゲルにおける悪無限:
- 「有限を超えてさらに有限を超えて…」と無限に繰り返す、果てしない進行。
- 例:1, 2, 3, … と続いて「終わらない」無限。
- 有限に対して「外に無限がある」とする二項対立であり、有限と無限が止揚されない。
ヘーゲルにおける真無限:
- 有限と無限の対立を止揚し、有限のうちに無限が現れていることを理解すること。
- 無限は有限から区別された「彼岸」ではなく、有限の運動・自己超克のなかに実現される。
- これはスピノザの「絶対的無限」に近いが、「絶対的無限」を実体(神=自然)として存在論的に規定するスピノザに対して、ヘーゲルは「真無限」を思考の弁証法的運動として論理学的に規定する。
- 「有限と無限の関係のあり方が問題だ」という展開。
- 「有限そのものが自己を超えて無限に至る」という弁証法的運動の契機となっている。
スピノザの対比は 存在論的区別(実体=絶対的無限 vs. ある属性に限定された無限)。
ヘーゲルの対比は 論理学的区別(有限を否定するだけの無限 vs. 矛盾を止揚して自己一致する無限)。
第一部 定義七
原文
Ea res libera dicitur quæ ex sola suæ naturæ necessitate existit et a se sola ad agendum determinatur. Necessaria autem vel potius coacta quæ ab alio determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione.
自訳
唯一その本性の必然性のみから存在し、それ自身のみから活動へと決定されるその事物は「自由なもの」と言われ、しかし限定されたある一定の仕方で存在し働くように他のものから決定される(その事物は)「必然的なもの」、あるいはむしろ「強制されたもの」(と言われる)。
語釈
Ea res 〜 dicitur 「その事物は〜と言われる」このフレーズが定義七全体のフレームになっている。
一文目でlibera(自由なもの)としての「その事物」の説明で「quæ ex sola〜ad agendum determinatur.」が関係代名詞の従属文となっており(先行詞はEa res )、二文目でNecessaria autem vel potius coacta(「必然的なもの」、あるいはむしろ「強制されたもの」)としての「その事物」の説明で「quæ ab alio〜ac determinata ratione.」が関係代名詞の従属文になっており(先行詞はEa res )、二文目では「Ea res 〜 dicitur」は省略されている。
ad agendum
ad existendum, & operandum adと動名詞の組み合わせは「〜するために」と訳す慣用表現。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p179 動名詞の対格)
existit
existendum 現に存在する。第一部 定義六のensの語釈参照。
dicitur 言われる。ヴァチカン写本と『遺稿集』ラテン語版では「dicetur(言われるであろう)」になっている。既出訳では上野訳のみ「言われるであろう」と訳している。
ab alio 他のものから。ここで言われる「他のもの」には意味の二重性があるということ。ひとつは、「外的な事物」つまり諸様態、もうひとつは「実体」。下記解説参照。
解説
主に第五部において語られる「自由な人間」。この定義はそこで重要になってくる。
以下の内容はYOUTUBEで佐々木晃也さんという方が言っていた内容を自分なりに要約したものになる。
佐々木さん曰く、スピノザの考える人間的自由の問題は「いかにして強制から解放されるか=自由になるか」ではない。
真の人間的自由の問題は「いかにして強制されつつ自由になるか」であるという。
一見スピノザの哲学において矛盾に思える問題に対して、どのように論理的な整合性をつけていくかという部分にスピノザ哲学のおもしろさがあるという話をされていた。
原典読解を通してスピノザの哲学を考察するとはこういうことなのかと勉強になった。
以下に自分の理解したことをまとめておく。
- ふつう、「自由」に対立するものは、「必然」と見なされているが、スピノザの場合、「自由」には 「強制」が対立し、「必然」はむしろ「自由」と等置されている。
(工藤・斎藤訳註より引用。) - 自由とは、絶対的な未決定ではなく、むしろ自己による決定即ち内的な決定であり、必然性に対立するのではなく、強制あるいは暴力に対立する、つまり他の事物による決定即ち外的決定に対立する (8)
注8:Martial Gueroult, Spnoza 1: Dieu. p77(YOUTUBEより抜粋。下記リンク参照)
自由=内的必然性 vs 強制=外的必然性
これまでの注釈者における一般的なこの定理の解釈(動画の中では、ゲルー・ドゥルーズ・マトゥロンなど第一・第二世代の解釈とされる)では、上記のように「自由と内的必然性」、「強制と外的必然性」それらが互いに対立しているという構図で考えてられていた。
しかし佐々木さん曰く、そうではないということだ。
まず、この定義では「自由なもの」と「強いられたもの」とは対立概念としては書かれていないということ。あくまでも並置である。
言い換えると、「自由なもの」が自己の内側からの内的必然性に従う。それに対して、「強いられたもの」が他の事物による外的必然性に従う、というように前者を肯定的な概念、後者を否定的な概念として対立させているわけではない。
定義の前半では、そのような「自由なもの」が実体にしか当てはまらない概念である、とは言われていない。むしろ諸様態から強制された事物でしかない人間が「自由な」と第五部では言われている。ここに一般的にみたら矛盾とも思えるスピノザの逆説が見出せる。なぜスピノザはそのようなことを考えたのか。
「他のものから(現に)存在し、働くことのために決定される事物」という部分で言われる alio「他のもの」には意味の二重性があるということが鍵になる。
その意味の二重性のひとつには、自分の外にある事物(外的な事物)いわゆる諸様態。様態としての事物であるわれわれ人間は、他の事物から決定されることなく存在することはできない。そもそも諸様態による外部強制からは絶対に逃れることができない。alio「他のもの」を普通に読めばこの解釈になるだろう。
alio「他のもの」の意味の二重性のもうひとつは「実体」。「実体」も様態ではない「他のもの」といえる(第一部 定義五より)。しかも様態が「実体」に内在している。
それゆえ 「他のものから(現に)存在し、働くことのために決定される事物」は二重の意味で言われている。すなわち、人間は一度に「他の事物 (諸様態)」 によってかつ「他の事物 (実体)」によって、つまり外的かつ内的に強制されている事物である。「他の事物」の意味の二重性は「強制」の意味の二重性をもたらす。
まとめると「他のものから(現に)存在し、働くことのために決定される事物」という部分で言われる「他のもの」には外的な事物から決定されるという意味と、実体から内的に決定されるという意味が包含されている。
以上のような解釈は、第二部 定理三九とその証明において「十全な原因」およびその知解を表現する「共通概念」においてより発展的に規定され、上記矛盾とも思えるスピノザの逆説もそこで回収される。
詳しくは動画を見てもらいたい。
またこのようなalio「他のもの」における二重性の問題は、佐藤一郎著「個と無限」でも「『エチカ』第一部の二つの因果性がめざすもの」として取り上げられており、「二重因果性の問題」として歴史的に論争を巻き起こしてきたテーマとも繋がるものだろう。詳細は下記の記事参照。
第一部 定義八
原文
Per æternitatem intelligo ipsam existentiam quatenus ex sola rei æternæ definitione necessario sequi concipitur.
自訳
「永遠」によって私は、永遠な事物の定義のみから必然的に出てくると考えられる限りで、現実存在それ自身のことと理解する。
語釈
sequi 論理的に帰結する。因果的に結果する。英語ならfollowに相当。
説明 原文
EXPLICATIO : Talis enim existentia ut æterna veritas sicut rei essentia concipitur proptereaque per durationem aut tempus explicari non potest tametsi duratio principio et fine carere concipiatur.
説明 自訳
なぜなら、そのような現実存在は事物の本質と同じように永遠真理として考えられ、それゆえにたとえ持続が始まりも終わりも欠けていると考えられようとも、持続または時間によっては説明されることができないからである。
語釈
carere careō の不定法。奪格支配で「〜が欠けている」を意味する。
concipiatur 接続法受動態現在。tametsiと呼応して譲歩の意味をとる『譲歩の接続法』。(山本太郎著「しっかり学ぶ初級ラテン語」p263 譲歩の接続法)
解説
スピノザにおいては「永遠」と「無限の持続」の峻別がなされているということ。
スピノザはここで、持続をprincipio et fine(始めも終わりもないもの)として無限に考えることはできるが、「永遠」をそのような時間的な無限延長とは異なるものとして定義している。
つまり「永遠」とは「時間に始まりも終わりもない持続」ではなく、æterna veritas(永遠の真理)や、rei essentia(事物の本質)と同じ仕方で把握される存在であるということ。
さらに、定義八における「永遠」と「無限の持続」の峻別は、定義六における「絶対的無限」と「その種類における無限(相対的無限)」の峻別とも構造的に呼応している。
☆定義六「その種類における無限(相対的無限)」(in suo genere tantum infinitum)
⇔
☆定義八「無限の持続」(duratio sine principio et fine)
- 「その種類における無限(相対的無限)」は、時間や広がりなど、特定の属性における限りで「無限」と呼ばれるもの(=持続や延長の無限)。これは「量的に限界を欠く」だけなので、スピノザにとってはまだ相対的なもの。
☆定義六「絶対的無限」(absolute infinitum)
⇔
☆定義八「永遠」(æternitas)
- 「絶対的無限」は、すべての属性において「無限」である実体=神であり、その本質そのものが「存在」を含んでいる。これは時間や空間に依存しない「永遠」に結びつく。
このようなスピノザにおける「相対的/絶対的」という構造的な峻別は、第五部で出てくる「人間の魂の永遠性」の問題とも繋がってくる。
簡単に触れておく。
第五部において「人間の精神はある意味で永遠である」と言われる。
『肉体が滅びれば、それに結びつく想像や記憶は消滅するが、しかし魂が「真理を認識する限り」=「神の知的愛」に参与する限り、その部分は「永遠」に属する。それは時間の中で続く「持続」ではなく、「永遠の秩序」において存在する。』
第五部をまとめると上記のようになるが、つまり魂の「永遠性」は「死後に時間的に存続する」という話ではなく、本質的に永遠なるものに参与する部分があるということになる。
それはそのまま第一部の定義六・八で出てきた「相対的/絶対的」という構造的な峻別とも対応する。
スピノザは一貫して「相対的無限と絶対的無限」を区別している。
- 相対的無限(持続) → 時間的に延長された有限性。魂の「個体的な」部分。
- 絶対的無限(永遠) → 本質そのものとしての必然性。魂の「真理に参与する」部分。
以上から、第五部で語られる「魂の永遠性」とは、「死後存続する霊魂」の話ではなく、後者の永遠に属する認識様態をもつ魂の部分を指していることがわかる。


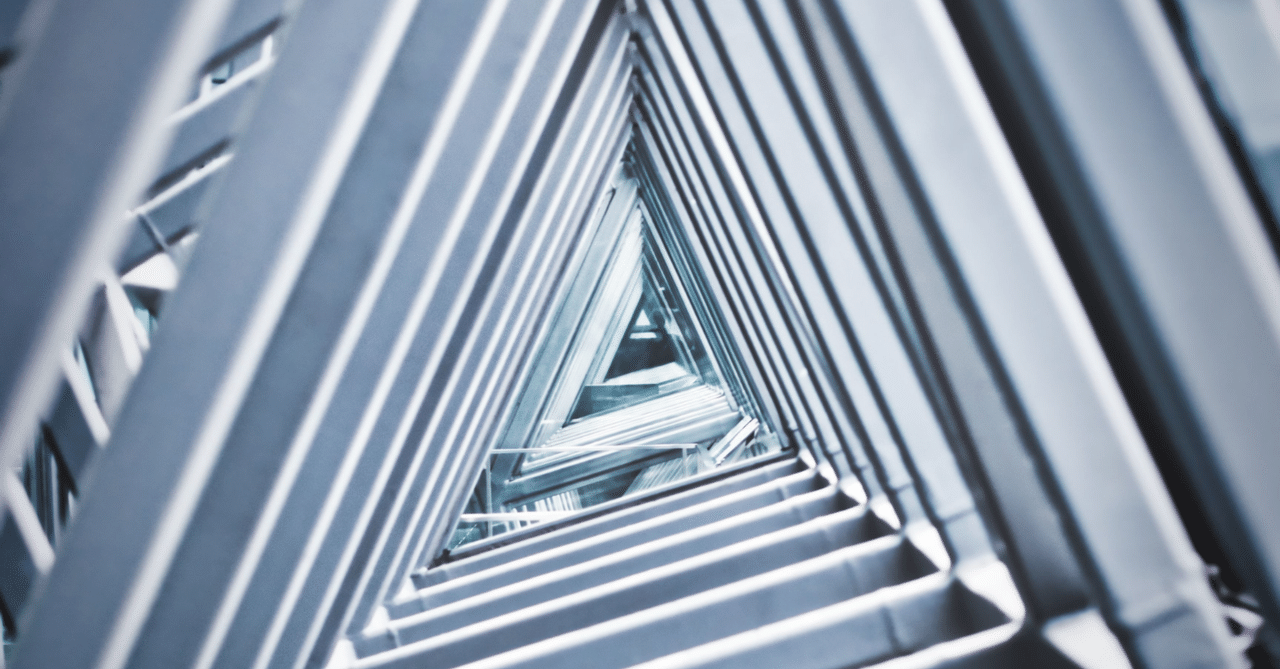




コメント