どうもOGKです。
今回は村瀬学『新しいキルケゴール』を読んでみて、印象に残った部分を取り上げ、自分の中にできたキルケゴール像について書いてみようと思います。
ただ、私自身キルケゴールに関する著作は本書が一冊目なので、一般的なキルケゴール理解とずれている可能性が大いにありますのでご注意ください。
一旦、現時点での私のキルケゴール理解ということで記事にまとめておきます。
なお、引用文中の強調は引用者によります。
弁証法を「反転の自覚」として理解したキルケゴール
つまり目標に到達しようと近づいているのだが、気がつくと事態は「反転」しており、目標から遠ざかることになってしまっている。「弁証法」なるものが、矛盾や対立物についての認識、あるいは量質転化、否定の否定についての認識というふうに言われてきたことは、ここでいう《反転の自覚》に集約される。先に示した「ルービンの壺の絵」は、二つの絵が一つの絵として現われる意味において、矛盾だと言えば矛盾だし、対立していると言えば対立しているし、そこには片方の絵から片方の絵への質的転化も起きているし、それがお互いを否定して出現し合うという否定の否定 も起きている・・・・・・ということになれば、ここにはいわゆる「弁証法」と呼ばれてきた基本的な問題がすべて出そろっていることになる。細かな異論は度外視するとして、こうしてみれば、「弁証法」 の性格を、「反転の自覚」として理解してゆくのは、あながち的はずれでないことがわかる。(p285)
著者は弁証法を「反転の自覚」とした上でさらに以下のように述べます。
「反転」というあり方の恐ろしさは、確実なものに到達しえないというところにある。こうした 「反転」という性格は、もともとは宇宙それ自体のもつ性格である。宇宙は「生成」そのものであり、不動不変、不生不滅なものは宇宙には存在しない。宇宙の性格は言ってみれば「万物流転」である。つまりこれが「確実」だと言えるものは宇宙には存在せず、万物は生じては消え、またどこからか生じてくる。
その宇宙の根本的な性格を「反転」と呼べば、それは決して不条理な言い方をしているわけではないのだ。ところが私たちは、そうした宇宙あるいは世界のもつ「反転的性格」を「認識」という形で受けとめ理解する。この認識として受けとめられた反転性への自覚形態が「弁証法」と呼ばれてきたものなのである。そして「認識」もまた「世界」の中に生起するひとつの出来事である限りにおいて、「認識」そのものもその根本に「反転的性格」を有している。だから「認識」を武器に、 世界や宇宙の「確実な真理」を手に入れようとする者は失脚することになる。そこに「認識者」が 「懐疑者」として現われざるを得ない理由がある。(p285-286)
そんなわけで「認識」に頼っているだけでは、確実なるものに少しも到達し得ない、そこに生じるのは「反転につぐ反転」でしかない、という立場が自覚された時、彼の中に「弁証法」なるものの総体が一気に把握されたのである。「弁証法」は決して確実的なものには向わない。むしろ確実なるものに向わないということを自覚するための方法であり、そういう自覚をうながすためには最良の方法であった。そして彼は「方法としての弁証法」をそこから自覚するに至るのである。(p286)
キルケゴールは、弁証法の果てに終着点を構想したヘーゲルを批判して、弁証法は「反転につぐ反転」でしかなく、決して確実なものには向かわないとし、むしろそのことを自覚するための方法として弁証法を捉えています。
それはキルケゴールの「美的 ⇄ 倫理的 ⇄ 宗教的」という考え方にも表現されています。
倫理というのは生活の基本であるというので、図の「中心」に描かれている。しかし「生活」に至らないからといって、その人の人生が人生でないのだという事はない。生活的でない様々な人生がありうる。この生活=倫理からの逸脱を世間では「美的」とか「宗教的」とか形容している所がある。そしてそういう世間的な言い方として、高貴な美的人格者もおれば、堕落した宗教的人格者もおる、と言われることが出てくる。このように生活=倫理からの逸脱の仕方としての「美的」「宗教的」の区別は、実に紙一重である。紙一重と言うのは紙一重さえ立てにくいという意味である。
たとえば異宗教同士がお互いの宗教のしきたりや作法を見ると、やたらとこっけいに見えたり、 軽薄に見えたりすることがある。異宗教同士からすればお互いのやり方は極端に「美的」に見えるところがある。身体を傷つけ、血をながし、踊り狂うような宗教を見て、美的享楽=美的陶酔にすぎないと見る人もおれば、坐禅を組み、滝に打たれるような宗教を見て、別な意味での、苦業享楽=美的陶酔にすぎないと見てとる人もありうるだろう。《イワシの頭も信心から》と揶揄されてきた事情がそこにある。異宗教からみたら「イワシ=美的なもの」にすぎないものが、当の宗教から すれば、十分「神事」になりうるのである。「信心」の力である。
キルケゴールは、そういう事情についてはよく自覚していたし、警戒もしていた。「宗教的」と呼ばれている事態は、別な角度、別な脈絡から見ると、おそろしく「美的」に見えるし、実際にも 「美的」なものに転化している場合があるのだと。これが「紙一重」と言ったことの意味である。 そして事実キルケゴールは「美的著作」と名づけた一連の著作の中で、いかに「宗教的」なものが 「美的」なものと極似しているか、あるいは「宗教的」だと思っているものが、いかに「美的」なものにすぎないかを徹底してあばき出していたのである。むろん「美的」だと批難されるものの中にいかに「宗教的」なものがあるか、という洞察も含めて。
このことを踏まえてみるなら、彼がしばしば持ち出している「三段階図式」というのが、いかに 作為的、詐術的な内容をもつものであるかがわかるというものである。もしキルケゴールの胸のうちを図化させてみれば、「三段階」は先に示した図のように描かれ、各「段階」は「領域」として、 常に相互に反転されてゆくものとして描かれなければならないはずである。それぞれの「領域」は 紙一重で日々反転されている。(p292-293)
ヘーゲルにとっての認識は「正 → 反 → 合」というような発展の道程を辿ります。例えばある局面においては「合」の方が「正」よりもより高い位置にあるように、これはある種の段階の概念になっています。それは「前ー後」つまり〈時間軸〉の関係といってもいいかもしれません。ヘーゲルのそれは一方通行で、決して後ろに戻ることはありません。
しかし、キルケゴールの「美的 ⇄ 倫理的 ⇄ 宗教的」という概念は、そのそれぞれがある領域を指し示しているだけで、各々が弁証法的に反転する構造になっていることを示唆しているにすぎず、そこに「高ー低」の区別や「前ー後」の区別はありません。
つまりキルケゴールにとっては、何度でも互いの領域に立ち戻ることがあり、相互の領域を行き来するような構造のみを弁証法の中に読み取っているといことです。
そのような構造の違いがヘーゲルとキルケゴールを分ける根本的な差異となっているのではないでしょうか。
「他者」の意識と相関的に現れる自己
たとえばありのままの生活の流れを考えてみる。
この場合の「私」なるものは、どこかに「在る」ようでいて、決して自体でどこかにポツンと 「在る」わけではない。「私」は妻の前では夫であり、女の前では男であり、子どもの前では親であり、街の中では市民である・・・・・・というふうなのだ。つまり、どこかの脈絡に入ることによって、はじめて「私」は具体的な何者かとして現われる。職場という脈絡にいるのに「夫」として立ち振まうわけにはゆかないし、妻との脈絡の中にいるのに一般「市民」みたいな立ち振まいをするわけにはゆかない。「私」というもののあり方は「私」をとりまく様々なレベルの脈絡=関連状況ぬきにはとうてい考えられないし、逆に私たちは、この脈絡=関連状況を意識することの中でしか「私」 を「何者」かとして出現させることはできないのである。脈絡がないのに「私」を「大統領」だと言っても、笑い話になるどころか、正気を疑われることにもなりかねない。(p293-294)
つまり、キルケゴールは複数の対象との関係性によって複数の自己がその対象ごとに措定される「自己の多者性」を見出しました。
そこにおいては、相対的な関係性ごとに自己は規定されることになるため、自己は常に移行し続けているもの、次々と何者かに成ってはまた、別の何者かに成り続ける過程としてしか捉えることができず、永遠に本質としての自己というものに到達することはありません。
キルケゴールは「死に至る病」でこのような「多者として存在する一者」のあり方を「絶望」と呼びました。
それはなぜ「絶望」なのでしょうか。
「帝王か、しからずんば無か」ということを考えている野心家の有名な説話がある。この説話を例にとれば作者の意図もわかりやすくなる。
彼は帝王になろうとしているがなれない。そのことについて彼は絶望している。しかしただ帝王になれないことに絶望しているのではない。「正確に言えば、彼にとって堪えられないことは、彼が自己自身から脱け出ることができないというのである。」これはどういうことなのか。問題になっているのは、彼が様々な自分(多者)を生きる可能性をもっているということである。可能性という点からみれば彼は確かに何者にでもなりうる。しかし彼は実際には思うような何者かになれない。そこでと作者は言う。もし彼が帝王になれたとしたらどうなるか。それもまた絶望だというのである。なぜなら、それもまたひとつの仮りの自分にすぎないから。彼は何に成ったとしても、また新たな可能性の自分が見えてくるだろうから。(p268)
つまり、自己自身が本質的な規定を持たないがために常に弁証法的な運動をつづけることしかできず、確固とした自己にいつまでも到達できないことをキルケゴールは「絶望」と表現したのだと思います。
そしてそのような「多者として存在する一者」は「他者」にかかわるところで発生するとされています。つまり自己像というものが「他者」の意識と相関的に現れるということでもあります。
作者が問うているのは「神」ではなく、あくまで自分が《相手》とする者によって 《自己》というものがつくられるのだという構造である。
「自己を量る尺度は、つねに、自己がそれに面して自己であるその当のものである、そしてこれがまた、《尺度》が何であるかの定義でもある。同質の量だけが加算できるように、あらゆる事物は、 それが測られる尺度になるものと同質である。そして質的にその尺度であるものは、倫理的にはその目標なのである。そして尺度と目標とは質的には事物の本質と同じである。ただし、自由の世界に関しては例外がある。ここでは人間が自分の目標であり尺度であるものと質的に異っている場合があるが、その場合、この質的堕落の責任はその人自身にあるにちがいない。だから、目標と尺度とはどこまでも目標であり尺度であって、それが裁き手となって、人間が彼の目標であり尺度であるものと同じでないことを暴露するのである。」
おそらく『死に至る病』の中で、最も優れた個所である。「自己」なるものは「自分」の中で創られるものではなく、自分が向い合う「相手」によって創られるものである。ここで言われる「尺 度」や「目標」とは《他者》以外の何物でもない。他者を尺度とし、他者を目標とすることの中で、 人間ははじめて自らを「自己」として意識してゆくのである。その結果として「自己意識」が生まれ、その自己意識の中では、他者はいてもいなくても関係ないようにして「自己」創造されてゆくのである。つまり「他者」に措定されて「自己」があるのであって、「自己」に措定されて「他者」 があるわけではないのだ。(p274-275)
このような考え方をキルケゴールはヘーゲルの弁証法から発想したのであろうし、それは以前に下記リンク先の記事の中でフォイエルバッハの説として紹介した考え方と酷似しています。(以下リンク記事参照。)
《実存》としてのあり方をめぐるキルケゴールのヘーゲル批判
このような弁証法的な発想自体、ヘーゲルが史上初めて明言したのだとすると、フォイエルバッハもキルケゴールもヘーゲルの一注釈者の範疇を出ておらず、ヘーゲル哲学の一バリエーションに過ぎないのではないでしょうか。
ただし、ここから『自他の』、『主客の』、『本質と存在の』統一を志向していくヘーゲルに対して、キルケゴールはそのようなあり方、つまり唯一の「自己」に到達することは決してできないが、それを求め続けること、成り続けようとすることにキリスト者としてのあり方をみたということができるのではないかと思います。
キルケゴールがこのどこにも見い出される《実存》というあり方を、なぜあれほどまでに強調しなければならなかったのかというと、ひとつにはヘーゲル哲学のように、自分では何物に成ろうと努力する=実存することもないのに、机の上で人間の「本質」なるものを思索して、「人間」のことがわかったような気になってしまうことの愚かしさをハッキリと批判するためであるのと、もうひとつは何の成り込みの努力もしないのに「キリスト者」でいられると考えている人々に対して批判をするためであった。キリスト教国に生まれたから「キリスト者」と認められたり、幼児洗礼を受けているから「キリスト者」であるなどと認められることはキルケゴールにとっては笑止千万であった。というのもそういう人は日々努力して「キリスト者」に成ろうと《実存》していなかったからである。つまり制度に登録されているだけで「キリスト者」と認定されているだけではないのかと。
もしこのキルケゴールの批判が、何らかの深い意味をもちうるとしたら、彼が当時のキリスト者に向けた疑問を、私たち自身の生活に向けてみることによって検証されうるだろう。というのも私たちは、「親」や「夫」や「妻」などを「制度」への登録としてすませてしまって、少しも日々にそれに成り込む《実存》として生きていないのではないかと。「夫」や「妻」として一旦登録されてしまったら、もはや努力してそれに成る必要がないかのように。
人間を「本質」ではなく《実存》としてみるという彼の生涯を賭けた思想の今日的な意義は、ここから再び切実なものとして見えてくるはずである。(p296-297)
このようにヘーゲルとキルケゴール、両者ともに弁証法という概念に立脚しつつも、その到達点は全く正反対になっていると言えます。
ラカンやスピノザとの類似性
ヘーゲルにとっては、弁証法的な発展の末に主客の統一が達成されますが、キルケゴールにとっては弁証法によってどこにも辿り着くことはできず、ただ空虚としての神、永遠に辿り着けない実体が措定されるとも言えます。
くり返しのべてきたように、「自己」なるものの成立根拠は「他者」にあり、その他者自体は自己にとって自己ならざるもの、つまり自己にとってうかがい知れないものとしてあった。つまり一旦成立した「自己」 にとって、その「自己」を成立せしめた「他者」のことは「わからない」のである。自己の支え手である他者は足下に隠れて見えないのである。こういう事情をソクラテスは《無知》と呼んだのだとしたら、こういう《自己のもつ他者性》すなわち《罪》は、ソクラテス流に「罪は無知である」と表現されるのは理屈に合っていると思えて、私にはしごく興味深く感じられたのである。(p277)
そのようなキルケゴール解釈においては、ラカンのシニフィアン、シニフィエの話やスピノザの「欲望対象の空虚性」の話との類似性を感じました。(詳しくは下記リンク記事にまとめています)
まとめるとキルケゴールは、「反転の自覚」として弁証法を定義し、あくまでもそれはどこにも辿り着かないし、何も終わらせることはできないものとして理解し、ただ一実存として自身の対象に成ろうとし続けることに目を向けることの重要性打ち出し、その価値を見出そうとしているということだと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
アドルノ『キルケゴール』を読むための肩慣らしとして読んでみましたが、キルケゴールについて大まかな雰囲気を掴むには、本書は優れていると思いました。
本書を読むと、キルケゴールがどのような論理でヘーゲルの哲学を批判し、自身の《実存》という考え方に至ったのかあらましを理解することができます。
キルケゴールがヘーゲルの哲学を批判するために弁証法を応用しているということがよくわかりました。
キルケゴールについてざっくりまとめると、
ヘーゲルの弁証法の発想を現実のさまざまな事例に応用し、認識における〈弁証法〉性、つまりは「反転につぐ反転」という避けることのできない性質を暴き出し、それら現実分析の結果として「他者との相関関係の中でのみ現れる自己」を《実存》として、そのあり方を追求することに価値を見出した。
と、私は理解しました。
本来ならここから、キルケゴール自身の著作に進むべきところなのですが、今回はあまり深追いせず本命のアドルノに進みたいと思います。
ではまた。
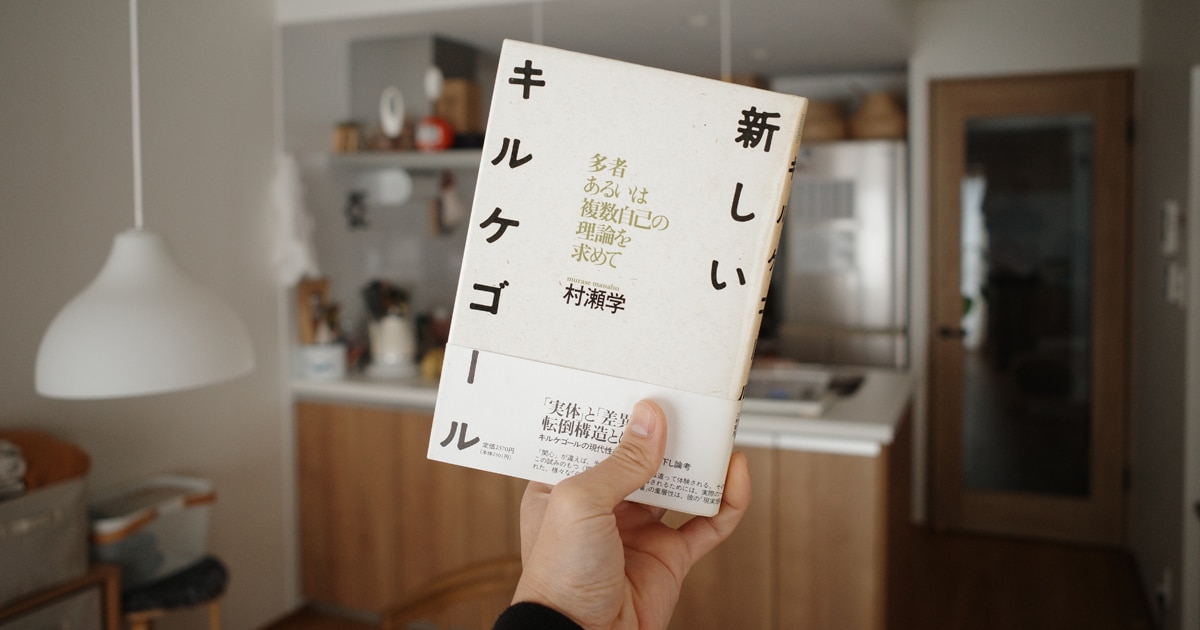





コメント