伊藤計劃「ハーモニー」というSF小説を読んだので読書感想文を記しておく。
いい作品なので多くの人に読んでもらいたい。
この記事自体は「ハーモニー」という作品自体の感想というより、その世界観に触発されて自分の日々の生活を振り返るという感じの文章になっていると思う。
なんというか生活のままならなさを感じていただければうれしい。
最近の自分の考えていることとして、デジタルデトックス、カフェインデトックスや睡眠の改善によって生活習慣を自制することで「少しでも日常生活を楽に過ごしたい」という意識が働いている。
つまるところ何と言っても普段の生活において仕事が一番の疲労とストレスの発生源であり、少しでも楽に仕事をこなしたいというモチベーションがすべてにおいて優先してしまっている。
これまでの経験から得た知識でもって身体や脳に過度な負担をかけることを避けて少しでも心身のコンディションが良い状態で日々を過ごせるようにしたいという意識に支配されているといってもよい。
行き着く先はまさに作中で描かれる健康至上主義の世界ではないか。
それは、身体と心に少しでも害のある物事は社会全体で排除して、自分の身体は自分一人のものではなく、社会全体のリソースとして第一に健康を維持する義務があるというものである。
しかし、私の現在の状況では日々の仕事から逃れるという選択肢はなかなか考えられない。
ストレスと疲労の発生源である仕事を排除できない以上、それとなんとか妥協してうまく付き合っていかなければならない。
そのためには、SNSばっかりやっているわけにはいかないし、コーヒーがぶ飲みして夜更かししてばかりもいられない。
そんなことで心身に不調をきたせば、その状態で仕事をすることのしんどさはなにより自分が一番わかっているのだから。
そう考えていくと、自分自身の現在の行動における主なモチベーションは「恐怖心」ということにならないか。
仕事において、思うように身体が動かない「恐怖心」、思うように頭が回らない「恐怖心」
それらに怯えて普段の生活習慣が形作られているとも言える。
それはある種の消極的な欲求であると思う。
私はその「しんどくなりたくない」という欲求と、その他のもろもろの欲求を天秤のかけ「しんどくなりたくない」という欲求を自ら意識的に選びとっているということになりそうだ。
ちなみに作中で「人間の意志」に関して以下のように述べられている。
そうだな、会議を想定しろ、と教授は続ける。
拡現のセッションでもリアルな集まりでも、どっちでもいい。
いろんな人間がアレやりたいコレやりたいとそれぞれの求めるものを主張し合い、煮詰めて調整し、結論を出す。人間が持ついろんな『欲求のモジュール』ってのが、その会議に参加して自分の意見を主張するひとりひとりだと思ってくれ。
そして、人間の意志ってのは、常識的に思いがちなひとつの統合された存在、これだと決断を下すなにかひとつの塊、要するにタマシイとかその類似物じゃなく、そうやって侃々諤々の論争を繰り広げている全体、プロセス、つまり会議そのものを指すんだ。意志ってのは、ひとつのまとまった存在じゃなく、多くの欲求がわめいている状態なんだ。人間ってのは、自分が本来はバラバラな断片の集まりだってことをすかっと忘却して、「わたし」だなんてあたかもひとつの個体であるかのように言い張っている、おめでたい生き物なのさ。
このように「人間の意志」とは絶対的なものではなく、迷いや逡巡の果てになんとか絞り出して選びとっていくような、そしてその選択に対して後になって後悔したりもする不完全なものであるということが言えるのではないか。
しかしそれとは別のもう一方の側面では、「しんどくなりたくない」というような消極的な欲求に対して私自身「不自由さ」や「閉塞感」を抱いていることもまた事実としてある。
もともとは「少しでも楽に心地よく生きていたい」という欲求であったもの、それを叶えるためには自分を律して日々の行動を自制という名のコントロール下に置かないとならないという状況。
「楽に心地よく生きるためには、自ら率先してしんどい思いをして自制しなければならない」
この袋小路のような根本的な矛盾。
その「自制をしなかった時のしんどさ」に比べたら「楽に心地よく生きるための自らに課す自制のしんどさ」の方がまだ幾分ましかな、というなんとも消極的な意識で日々の行動を選びとっているとしか思えない。
それに対しては「酒は百薬の長」という言葉さえあるように、何事にも正の側面、負の側面それぞれがあり適度を守ればマイナスもプラスに変えることができるのではないかと思われるかもしれない。
しかし自分の個人的な感覚にはなるが、適度を守れた試しがない。
自分にとっては「100か0」であり、「圧倒的な堕落か完全な自制」のどちらかに収束していく。
一度SNSを見ることを自分に許せばたちまち空き時間はすべてSNSに奪われていく。適度なバランスなんてものを保てた試しがない。
くだくだと書いてきたが結論として、少しでも楽に心地よく生きるためには自分を律し、日々の生活において自制しなければならない。
現時点でそれは変えようのない事実。
そのために日々の生活において「しなければならない自制」を自分にとって少しでも「心地よいもの」にしていくことはできるのではないかということ。
つまり自制のしんどさみたいなものはその人の捉え方次第でなんとでもなるとも言えるから、自分にとって至って自然に「日々の生活における自制的行動」を選択できるように日常をデザインしてしまえばいいのではないか、ということ。
でもそれってかなり作中でいうところの「人類のハーモニクス(人間から意志とか意識が奪われた状態)」に近づいているのではないかと思ったりもする。以下引用
どんな意志が必要だっていうの。問題はむしろ、意志を求められることの苦痛、健康やコミュニティのために自身を律するという意志の必要性だけが残ってしまったことの苦痛なんだよ
できるだけ脳内での欲求同士の葛藤を少なくして、ストレスを減らして、できるだけ自然にもっとも健康負荷の少ない行動を選択できるようにしていくこと。
つまりは自制的行動の自動化。
最適な行動パターンを無意識にでも選び取れるようになれれば、日々の生活は楽になるだろうし、当初の「少しでも楽に過ごしたい」という目標は達成されるのかもしれない。
わたしは内なる声に耳を傾けようとする。意識が、意志がなくなれば、こんな「内なる声」などというものも消滅してしまうのだろう。意識が、個が消滅し、ただシステムだけが残るのだろう。自明なわたしだけが残るのだろう。ただ、そう在るように行動し、一切の迷いなく、未来永劫に向かって働き続ける肉で出来た機能のような身体があるだけになるのだろう。
調和を描く脳は、一切の迷いを排した、いや、廃した人間だ。
迷いがなければ、選択もない。選択がなければ、すべてはそう在るだけだ。
その風景は、いままでの風景とまったく代わり映えしないものであることも判っている。人間の意識がこれまでも大したことをしてこなかった以上、それが無くなったところで何が変わるというわけでもあるまい。
昨日と同じように、人は買い物に行くだろう。
昨日と同じように、人は仕事場に行くだろう。
昨日と同じように笑うだろう。
昨日と同じように泣くだろう。
単純に自明な反応として。単にそうするべきだからそうするものとして。
「でも本当にそれで生きていると言えるの?本当にやりたいことを犠牲にして勝ちえた楽園に意味はあるの?」と、この作品は問いかけているのだろうと思う、きっと。
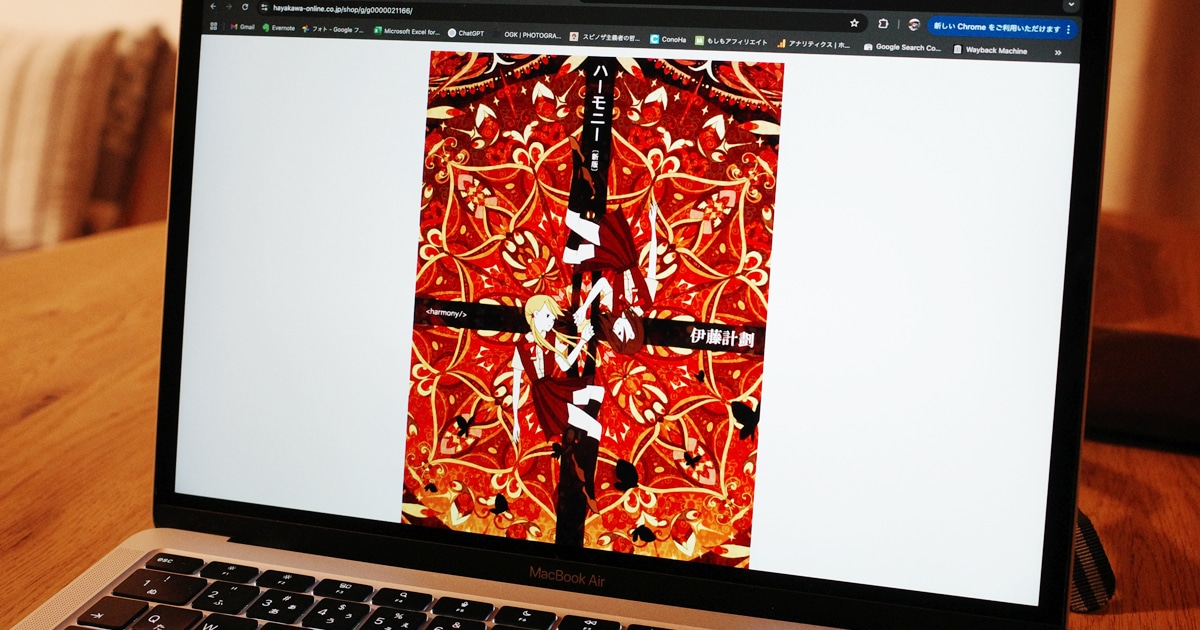



コメント